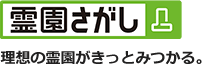お盆とお彼岸は、日本の伝統的な先祖供養の習わしで、年中行事の中でも重要な仏教行事です。
お盆の習わし
お盆は、先祖の霊が家に帰ってくるのを出迎えるための仏事で、正式には「盂蘭盆会」(うらぼんえ)といいます。
お盆の時期は、7月13日から16日までの4日間ですが、旧暦の8月13日から16日までに営むところも多く、地方によってさまざまです。
「お盆入り」の13日に霊が自宅に戻り、「お盆の明け」の16日に霊界に戻るとされています。 精霊棚を作り、先祖の霊が現世との往復に使う乗り物として、馬の形をしたキュウリや牛の形をしたナスを供えます。現在では、仏壇の前に小机を置いて、果物やお菓子、花などをお供えする場合が多いようです。
「お盆の入り」の夕方には、先祖の霊が迷わないように迎え火を焚き、16日の「お盆の明け」には送り火を焚きます。
地方によっては、白樺の皮や麦わらを焚くこともありますが、都市部ではロウソクの火を灯すだけで済ませる場合が多いようです。
「盆提灯」や「灯籠」なども、先祖が家に帰るための道しるべとされ、お盆の期間中は、仏前に飾っておきます。
新盆(初盆)のしきたり
家族が亡くなって初めて迎えるお盆を「新盆」もしくは「初盆」といい、とくに手厚く供養します。 精霊棚には通常の供物の他にも、故人が好きだった食べ物や飲み物などをお供えします。さらに、親族や友人たちを招き、僧侶に読経をしていただいてから、精進料理でもてなします。
お彼岸の習わし
お彼岸は、もともと「迷いの多い現世(此岸)から川の向こうの悟りの世界(彼岸)に渡ることを願って、行いを慎む期間」で、正式には「彼岸会」といいます。
時期は、3月の春分の日と、9月の秋分の日の前後3日ずつの合計7日間で、初日を「彼岸の入り」、最終日を「彼岸明け」といいます。
お彼岸には、お盆のような行事はとくにありませんし、仏壇を飾る必要もありませんが、「彼岸の入り」の前には仏壇を清掃し、花や水を替えましょう。
また、故人の好物だったお菓子や果物をお供えしますが、春にはぼたもち、秋にはおはぎを供える習わしがあり、これは「春の牡丹」、「秋の萩」という季節の花が由来だといわれています。 お彼岸には家族揃ってお墓参りをして、先祖を供養しましょう。
墓地・霊園選びでお困りですか?
「霊園さがし」は、全国の墓地・霊園情報を掲載したポータルサイトです。さまざまな条件から、あなたの探しているお墓を見つけることができます。まずは以下からお探しのエリアをお選びください。

墓地・霊園選びでお困りですか?
「霊園さがし」は、全国の墓地・霊園情報を掲載したポータルサイトです。さまざまな条件から、あなたの探しているお墓を見つけることができます。まずは以下からお探しのエリアをお選びください。

この記事を読んだ方はこんな記事も読まれています
-

納骨堂と合祀墓
目次1 納骨堂とは?2 合祀墓とは? ライフスタイルの多様化や家族形態の変化、墓地不足の深刻化などによって、自分や家族専用のお墓を建てない人が増えているようです。 そうした背景の中、注目されているのが「納骨堂」と「合祀墓 […]
納骨堂と合祀墓
-

納骨式の服装マナーを解説。喪服?家族ならカジュアルでも良い?
目次1 納骨式の服装は時期によって異なる1.1 四十九日以前の納骨式の正しい服装1.1.1 親族の服装1.1.2 参列者の服装1.2 四十九日以降の納骨式の正しい服装1.2.1 親族の服装1.2.2 参列者の服装2 納骨 […]
納骨式の服装マナーを解説。喪服?家族ならカジュアルでも良い?
-

お墓の建て替えは必要?
目次1 可能です、お墓の建て替えと修繕2 お墓の建て替えと修繕が必要な訳3 主な建て替えと修繕について4 まとめ 可能です、お墓の建て替えと修繕 日本では近年、規模の大きな地震が全国各地で頻発しており、地震が起こる度に墓 […]
お墓の建て替えは必要?
-

供養の意味や目的とは?故人を偲ぶだけではない?供養の行い方も解説
目次1 供養とは?種類も解説1.1 そもそも供養とは?1.2 供養の種類にはどんなものがある?2 供養の目的とは?故人を偲ぶだけではない?2.1 亡き人の魂が安らかであることを祈る2.2 一族の歴史を知り、絆を深める2. […]
供養の意味や目的とは?故人を偲ぶだけではない?供養の行い方も解説