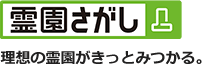お墓を継いでいくために必要なことがあります。
お墓の継承・引越霊園・墓地を入手する際には、永代にわたってお墓参りができるよう後々のことを考慮しましょう。
墓地の使用権取得者が亡くなった際には、お墓を継ぐ「継承者」が必要になります。また、諸事情でお墓参りが困難になると、お墓の引越「改葬」を行う場合も出てきます。
継承
お墓の使用権取得者を変更することを「継承」といいます。
一般的には長男が継承するのが習わしになっていますが、親族なら誰でもかまいません。親族間での継承が困難な場合は、被相続人の指定と家族の同意書があれば友人でも継承することができます。
継承者を指定する場合は、墓地の管理者に対し墓地使用者の名義変更届を提出します。被相続人の指定は、遺言、または生前の指定でもかまいません。
公営墓地では、継承者を親族のみとするところが多いので確認してください。その他の霊園・墓地によっても、お墓の使用者の姓の変更を認めないところもあるようなので確認が必要です。
どうしても継承者が決まらない場合は、家庭裁判所が継承者を指定することになります。継承者がいなくなり、管理費の支払いが滞ってしまった場合、永代使用権が取り消されることがあるので注意しましょう。
引越/改葬
墓地が遠くてお参りができない、家族の合祀墓にまとめる、他の宗教に改宗した等々、それぞれの理由でお墓の引越を余儀なくされることがあります。
このとき、お墓を別の場所に移すことを「改葬」といいます。改葬は、お墓や埋葬についての法律「墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)」に従って行わなければなりません。
お世話になった霊園・墓地へは改葬理由を説明し、事前に理解を得ておきましょう。元の墓地から遺骨を引き上げるときには、僧侶にお願いして「お魂抜き」という儀式を行います。
元の墓地の永代使用料は返還されません。また、更地に戻す「現状回復義務」があり、諸費用は自己負担しなくてはなりません。
遺骨だけでなく墓石の移設も希望する場合は、移転先が移設の許可をしているか確認する必要があります。
改葬にはさまざまな法的手続きが必要です。
元のお墓のある市区町村の役場で「改葬許可証」を交付してもらいます。「改葬許可証」は、「改葬許可申請書」、墓地管理者が発行する「埋葬証明書」、新しい墓地管理者が発行する「受け入れ証明書」の書類3点を提出すると交付されます。
分骨の場合は、役場への申請は必要ありません。元の墓地管理者から発行してもらった「分骨証明書」を、分骨先の管理者へ提出します。
墓地・霊園選びでお困りですか?
「霊園さがし」は、全国の墓地・霊園情報を掲載したポータルサイトです。さまざまな条件から、あなたの探しているお墓を見つけることができます。まずは以下からお探しのエリアをお選びください。

墓地・霊園選びでお困りですか?
「霊園さがし」は、全国の墓地・霊園情報を掲載したポータルサイトです。さまざまな条件から、あなたの探しているお墓を見つけることができます。まずは以下からお探しのエリアをお選びください。

この記事を読んだ方はこんな記事も読まれています
-

永代供養墓とは?その特徴とは?正しい情報を知ろう
目次1 永代供養墓とは何か1.1 家族に代わってお寺や霊園が管理をするお墓1.2 永代といっても未来永劫ではない2 永代供養墓がおすすめの方2.1 お墓を管理できる候補者がいない方2.2 できるかぎりお墓に費用をかけたく […]
永代供養墓とは?その特徴とは?正しい情報を知ろう
-

霊園・墓地の種類
目次1 墓地の形態は、管理・運営によって3種類。1.1 公営墓地1.2 民営墓地1.3 寺院墓地 墓地の形態は、管理・運営によって3種類。 お墓を建てるには、まずどこに建てるのか、その場所となる墓地・霊園を探さなくてはな […]
霊園・墓地の種類
-
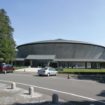
納骨堂の管理費を滞納したらどうなる?対処方法や基礎知識を解説
目次1 そもそも納骨堂の管理費とは1.1 管理費とは納骨堂の運営元に払う年間費用のこと1.2 管理費の相場は1万円から2万円2 管理費の支払いや滞納について2.1 お墓の購入者かそれを引き継いだ人が支払う2.2 滞納する […]
納骨堂の管理費を滞納したらどうなる?対処方法や基礎知識を解説
-

「博多霊苑」を筆頭に博多周辺の人気霊園・墓地を紹介
目次1 福岡市内から30分、人気の博多霊苑とは?1.1 人気の博多霊苑の費用1.2 お墓には何人まで入れるのか1.3 永代供養はできるのか2 博多から近い人気霊園・墓地・納骨堂2.1 4世紀の歴史刻む名刹の供養墓「青龍山 […]
「博多霊苑」を筆頭に博多周辺の人気霊園・墓地を紹介